副業を認めない会社の業種・傾向は?推進している企業はわずか6.8%!
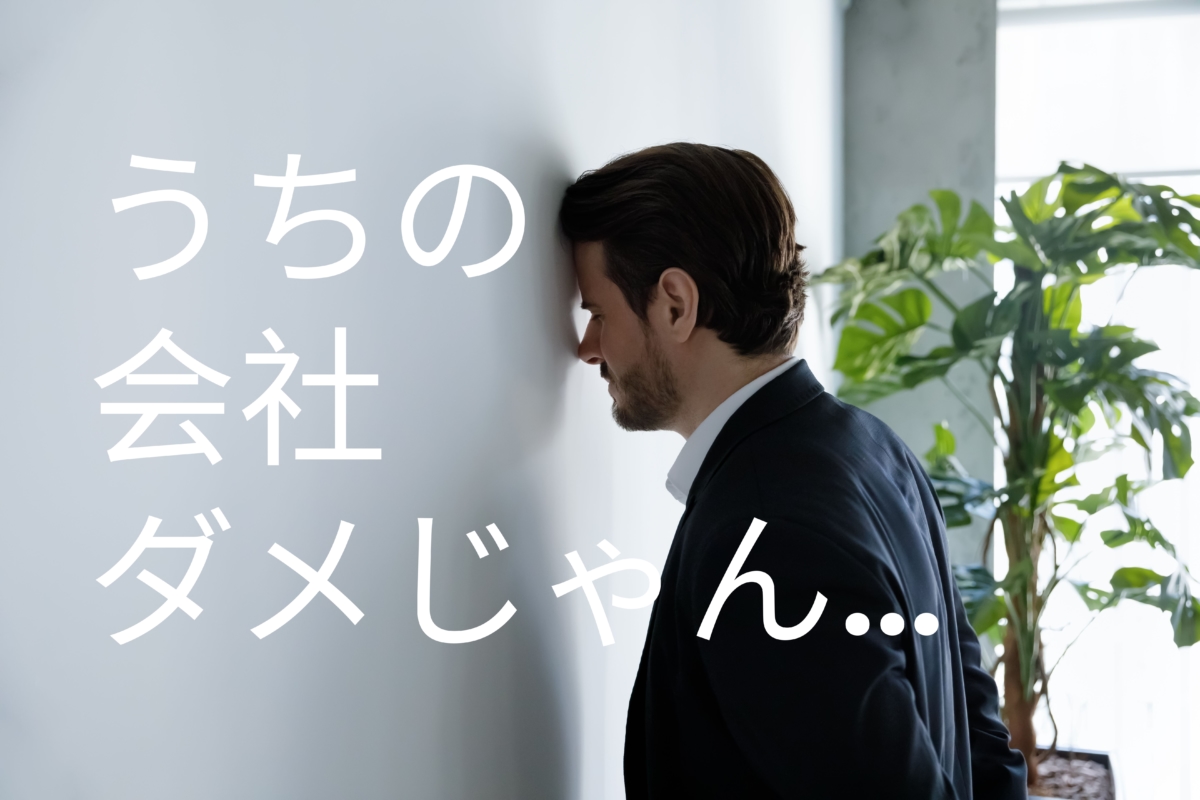
近年、生活費や将来の不安に備えるため、副業を希望する人が増加しています。また、収入を補うだけでなく、新たなスキルを身につけたり、趣味を活かしたりする場としても注目される一方で、さまざまな課題やリスクも存在しているのが実情です。そこで、副業に関する調査結果をもとにその実態に迫り、副業を検討する人々にとって有益な情報を提供していきます。
今回は、企業人担当者1,648人に対して行ったリクルートの「兼業・副業に関する動向調査」の結果などを基に、副業を認めている(推進している)企業の状況をまとめました。
「推進派&容認派」は大企業になるほど増える
副業を認める・推進する企業のニュースをインターネットやテレビで見ると「時代は変わった」と感じます。
ただ、印象ではなく実態として、従業員に対して積極的に副業を勧める(あるいは認める)企業はどのくらい存在するのでしょうか。
株式会社リクルート(東京都千代田区)が2023年(令和5年)に行った「兼業・副業に関する動向調査」によると、従業員の兼業・副業を認める人事制度を導入している企業は全体の51.8%でした。
前年の同調査の結果が50.5%なので、微増している傾向が確認できます。
ただ「認める」の中でも、認め方のスタンスは企業によって異なるはずです。
兼業・副業の人事制度を導入している企業の中でも「認める・容認する」と「推進する・推奨する」の割合は、前者が86.9%、後者が13.1%でした。
人事制度を導入していない企業も含め、副業・兼業に対する企業全体のスタンスを整理すると次のような割合になっています。
副業を認める人事制度なし・・・48.2%
副業を認める人事制度あり(容認派)・・・45.0%
副業を認める人事制度あり(推奨派)・・・6.8%
この「推進派&容認派」の数字は大企業になるほど大きくなる傾向があります。
日本経済団体連合会(経団連)が2022年(令和4年)に公開した「副業・兼業に関するアンケート調査結果」でも同様の傾向が確認できます。
経団連の会員企業全体の53.1%が社員の副業・兼業を認める中、従業員の数が多い会員企業(5,000人以上)の場合は「認める」が66.7%に達していました。
反対に、企業の従業員数が小さくなるほど、副業が認めらない傾向が明らかにされています。
副業を認める・認めない企業の業種とは
業種別には、どのような業種で副業が認められる・認められない傾向があるのでしょうか。
経団連の「副業・兼業に関するアンケート調査結果」によると、副業を認める企業の割合として全体平均の53.1%を上回った業種は次のとおりでした。
不動産業・・・85.7%
金融・保険業・・・76.0%
電気・ガス業・・・60.0%
製造業・・・54.0%
情報通信業・・・53.3%
逆に、全体平均を下回った業種は、
鉱業・・・0%
サービス業・・・34.8%
商業(卸売・小売)・・・41.4%
建設業・・・41.7%
運輸業・・・50.0%
となっています。副業・兼業を認めない理由については、経団連の「副業・兼業に関するアンケート調査結果」には記載がありません。
しかし、リクルートの「兼業・副業に関する動向調査」には、兼業・副業を禁止する企業側の理由が明らかにされています。
1位・・・従業員の長時間労働・過重労働を助長するため(51.0%)
2位・・・従業員には本業に集中してもらいたいため(46.8%)
3位・・・労働時間の管理・把握が困難なため(43.0%)
全体平均を下回った業種の多くは、長時間労働や慢性的な人手不足が長らく問題視されています。労災補償状況でも、ワーストランキングに入っているケースが多いです。
副業を認める企業の割合が全体平均を下回った業種で副業が認めらない傾向があるとすれば、労働時間や過重労働の問題がひとつ、企業側の判断に影響していると考えられます。
[文/坂本正敬]
[参考]
※ 「副業・兼業に関するアンケート調査結果」を公表 – 週刊経団連タイムス
※ 兼業・副業に関する動向調査データ集2022 – リクルート
※ 令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します – 厚生労働省