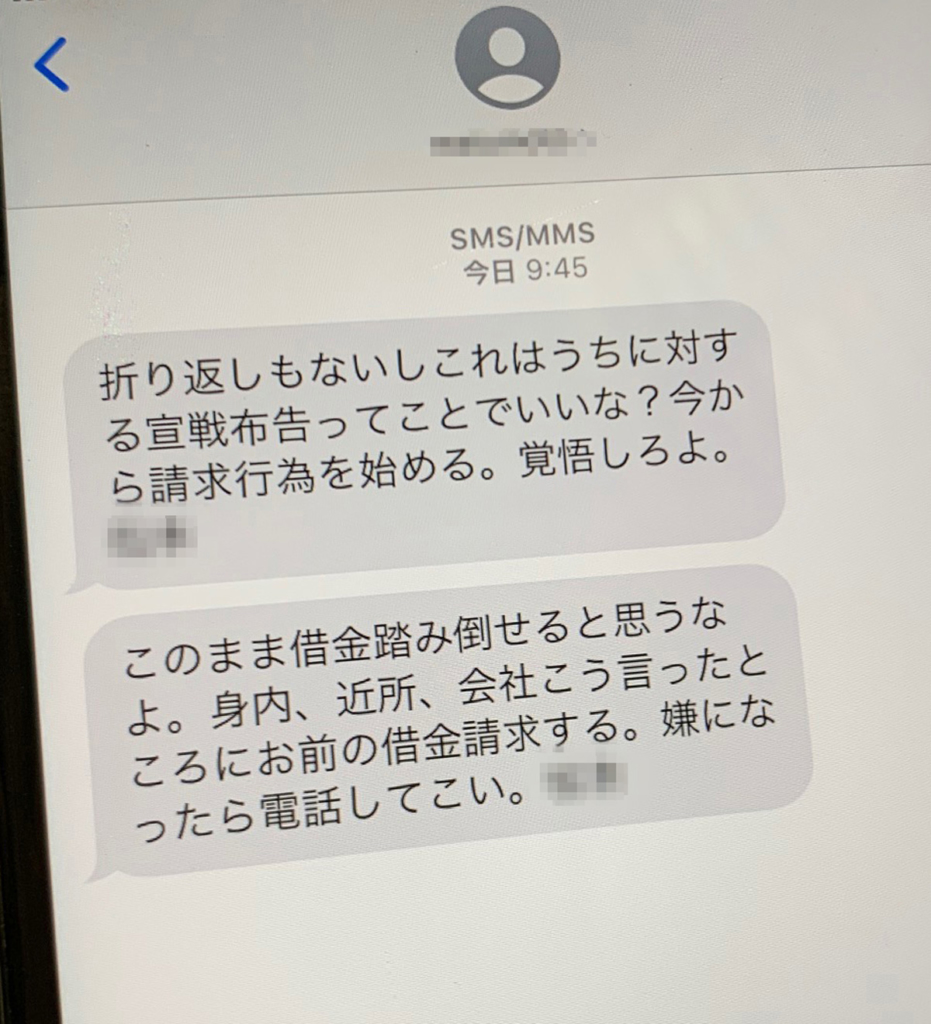コロナ貧困を黙殺する社会の闇。“普通の青年”DaiGo氏を変えたもの<森達也×藤田和恵対談>
安全圏からの報道が増えたと感じる
藤田:客観性、中立性といえば聞こえはいいですが、実際には「どっちもどっち論」的な安全圏からの報道が増えたと感じます。私が今回の同行取材を始めたのは、食料配布の現場で出会った、ある30代の女性がきっかけです。
彼女はコロナ禍で仕事を失い、給付金の審査業務の派遣にありつきました。しかし、「いつまた切られるかわからない」という不安と激務で憔悴し、ついに連絡が途絶えた。
なぜ一人のひたむきな女性が、コロナ禍の闇に消えたのか? 私自身が、その現実を知りたかったのです。
森さんは、DaiGoさんが普通の青年だったと言いましたが、彼は多様な現実を知らずに世界を知った気になり、差別や偏見に取りつかれてしまった。その病理こそ根深い問題だと思います。
平穏が、差別や偏見を生み出す
森:異物に対する忌避感と集団化への過剰な希求は、彼特有のものではなく、日本の社会全体が共有しています。刑事司法の取材でノルウェーに行ったとき、刑期を終えた受刑者が社会復帰するための住居が、普通の住宅街の中にあったことに驚きました。市民も「刑期を終えたのだから、何の問題があるの?」と受け入れている。
藤田:海外には「ハウジングファースト」、つまり社会復帰のためには、まずは住まいをという考え方があるそうです。一方で、日本は隔離して社会的に抹殺する。でも、見たいものだけを見て、心地よい言葉だけを聞いて得られる平穏は、差別や偏見を生み出すだけです。
森:コロナ禍で何が起きているのか? 知らずにいることを知り、目を向けてみる。メディアを含めたすべての人が、この社会を考える上で必要なことだと思います。
<取材・文/宮下浩純 撮影/芝山健太>
【藤田和恵】
ジャーナリスト。北海道新聞社会部記者を経てフリーに。’20年に「貧困ジャーナリズム賞」受賞。最新刊は、生活困窮者支援の現場に約1年間、密着取材したルポルタージュ『ハザードランプを探して 黙殺されるコロナ禍の闇を追う』(扶桑社)
【森 達也】
映画監督。作家など多彩な顔を持つ。明治大学特任教授。’98年、オウム真理教を題材にした『A』で高い評価を得る。監督作に『FAKE』『i−新聞記者ドキュメント−』など。小説『チャンキ(論創社)が10月1日に復刊