不老長寿は夢じゃない!?衝撃の“若返り研究”最前線を直撃取材
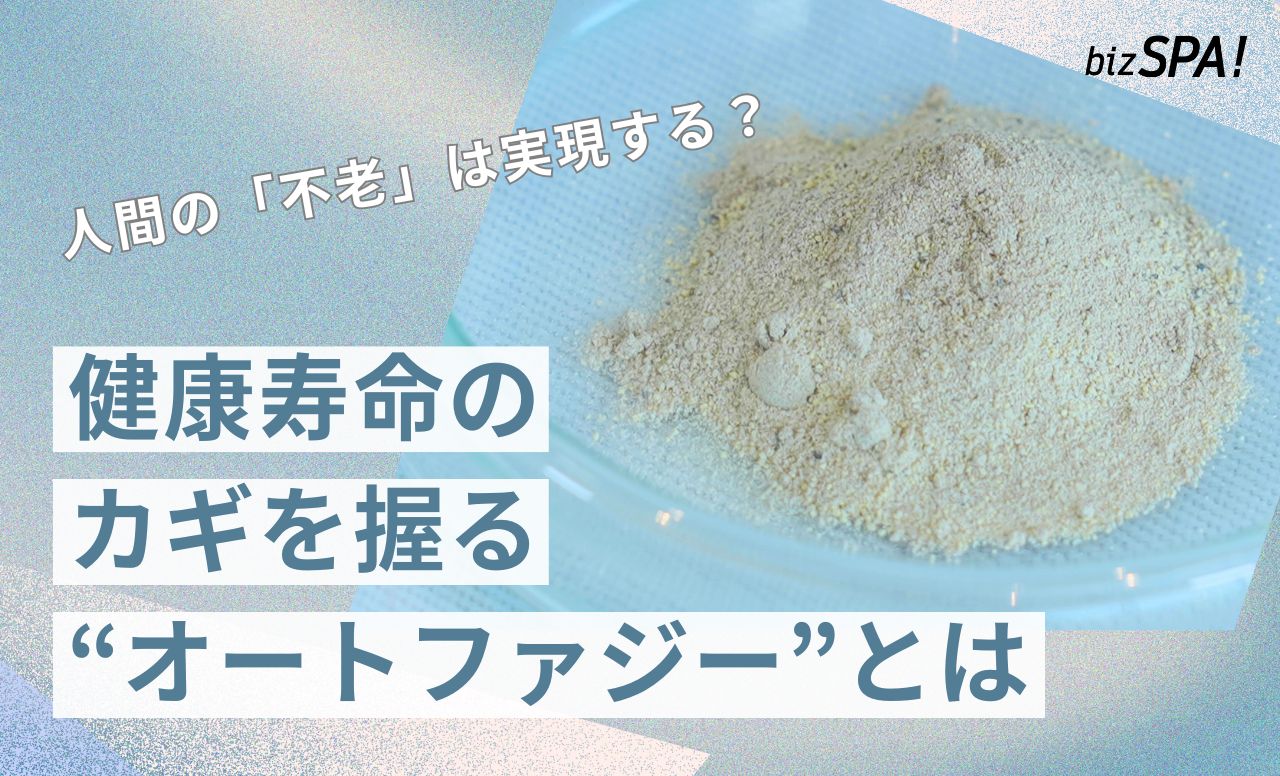
アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏やOpen AIのCEOサム・アルトマン氏など、世界の大富豪が今、こぞって「老化制御」の分野に投資を行っている。古くはクレオパトラや始皇帝も、永遠の命や永遠の若さを願ったと伝えられる。果たして人類が「不老」を手に入れる日はくるのだろうか?
不老の鍵を握る「オートファジー」研究の第一人者である大阪大学の吉森保名誉教授と、世界初の植物エキスでオートファジー活性成分を発見した株式会社ファインの佐々木義晴取締役に、世界と日本の不老研究の今について話を聞いた。
目次
人間は本当に若返りが可能なのか?

――最初にズバリうかがいたいのですが、老化を防げるようになるというのは本当ですか?
吉森:はい。私だけではなく世界中にいる多くの研究者は現在、老化、さらに死を回避することは可能だと考えています。
その一番わかりやすい根拠は、老化しない生き物や死なない生き物が見つかっているということです。例えばアフリカにいるハダカデバネズミは老化しません。普通のネズミの寿命は3年なのに対し、ハダカデバネズミの寿命は30年。見た目も変わらず、病気も体力の衰えもなく、生きている間健康を維持したまま、ある日突然パタっと死にます。
また、老化の話からは逸れますが、ベニクラゲというクラゲは死にません。こうした生き物がいるという事実が、老化や死が必然ではないことを示しています。
人間の不老への道はいろいろあると思いますが、私はオートファジーが非常に重要であると考えて研究を進めています。
健康長寿の鍵を握る「オートファジー」とは
――「オートファジー」とはどういうものなのでしょうか。
吉森:まず、生き物は全部細胞からできていて、病気も老化も必ず細胞で起こります。
オートファジーというのはこの細胞の中のメンテナンスを行う一連のシステムです。細胞の中にはたんぱく質や脂質などいろいろなものがありますが、オートファジーがそれらを回収、運搬、分解、再生しています。
さらに細胞の中で有害物質、つまりは病原体や認知症の原因となるたんぱく質のかたまりなどが発生すると、細胞内社会における「回収業者」であるオートファゴソームという袋が、狙い撃ちで除去することがわかっています。健康を維持する上でオートファジーは非常に重要な役割を果たしているのです。
――では、なぜ人間は病気や認知症になるのでしょうか?
吉森:オートファジーは非常によくできた仕組みですが、年をとると機能が低下し、これにより病気や老化が起こることがわかっています。
つまり、オートファジーの低下を阻止すれば健康が維持できるはずです。そのように考えてオートファジーを促進するためのチャレンジを続けているわけです。
薬ができるのはまだ先ですが、オートファジーに着目したサプリはすでに世の中に登場しています。
佐々木:弊社は1974年に創業したサプリや健康食品を扱っている企業です。オートファジーのメカニズムに着目し、研究を行ってきました。
4月にはオートファジーを活性化させることがわかった植物由来のエキスをミックスして『ファイン オートファジーReCell』というサプリを発売しています。オートファジー活性については、吉森先生が共同代表を務める株式会社AutoPhagyGOさんにおよそ500種類の植物抽出物のスクリーニングを依頼し、実証いただいたものです。

世界では「老化制御」の研究に熱視線が注がれている
――今、世界ではこのリバースエイジング、若返りの分野が一種のムーブメントになっているそうですね。
吉森:はい。アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏やOpen AIのCEOサム・アルトマン氏、そしてグーグルなどにより民間資金が投じられており、さらにアメリカなどでは国家政策として老化研究が進行しています。
佐々木:特に欧米では「Longevity(長寿)」というキーワードが非常に注目されていますよね。世界的な長寿医学本『OUTLIVE』でもオートファジーは重要なファクターとして紹介されています。
――それに比べると、日本では大きな盛り上がりが感じられません。
吉森:そうですね。背景にはいろいろありますが、日本では「ちょっとお肌の状態を良くしたい」とか「ちょっと元気になろう」というようなアンチエイジングとしての捉えられ方が一般的で、本質的なところが理解されていないのだと思います。
他国で国家プロジェクトになっているように、実際には老化制御の研究は国家的課題の解決の糸口になり得るものです。
佐々木:特に日本は超高齢化社会に突入していますからね。日本は平均寿命に比べて健康寿命が約10年短いといわれています。せっかく長生きしても、健康寿命を延ばせなければ幸福度が下がってしまいます。
また、国民皆保険制度で一見守られているように思えますが、医療費増加の問題は深刻です。弊社がオートファジーに注目したのも、日本の課題と向き合ったとき、セルフメディケーションを推進する上でも重要だと感じたからです。
吉森:そのほかにも他国との違いはあります。例えばアメリカだと大学で何か新しいことが見つかればすぐにベンチャーが立ち上がって支援し、ある程度研究に目処が立つと大企業が引き継いで世に出すというシステムが確立されています。
実はオートファジー分野でも基礎研究は日本が世界をリードしているんです。そもそもオートファジーの研究が加速したきっかけを作ったのは、ほかでもない、私の師匠でありノーベル賞受賞者の大隅良典先生という日本人です。
一方で日本は特許など社会実装には弱く、中国やアメリカ、韓国にも負けてしまっています。
歯がゆい状況ではありますが、国にばかり頼っていてもいけないと思うので、私もベンチャーを立ち上げました。そこで儲かったら、それでまた研究をして……というのを繰り返せたらいいなと思うんですけど、まあ理想の話です(笑)。
アカデミアと産業界のタッグで研究を加速

――企業と連携することについては、どのように感じていらっしゃいますか。
吉森:私は研究者と企業との連携はどんどんやるべきだと考えています。
国は組織が巨大なので、フットワーク軽く動くわけにはいかないんですね。そうした中で産業界の理解のある人と直接一緒にできるなら、国とやるよりずっと迅速に動けますし、国が悩んでいる間に先に行くこともできます。
――AutoPhagyGOさんはアメリカの『XPRIZE Healthspan』という「人間を10年若返らせる」ことを競うコンペにも、ほかの企業と連携して参加されていますね。
吉森:3社合同チームで参加していますが、それだけではなく、ファインさんしかり、多くの参画企業がデータ取得や分析などで連携していますし、ほかにもスポンサー企業の協力を得ようとしています。
佐々木:AutoPhagyGOさんからのお声がけだったのですが、弊社は「世界中の人の健康寿命を10年延伸させる」という企業ミッションを掲げており、今回のコンペのテーマがまったく同じだったので参加を決めました。
吉森:産業界といってもいろんな会社があります。例えば化粧品でオートファジーという言葉はたくさん飛び交っていますが、どこまで実証しているかは正直わかりません。
その点、ファインさんはすごく手間をかけて、科学的なエビデンスを大事にされています。やっぱりそういうところと一緒にやっていきたいなというのはあります。
「若返り」という人類の夢を叶えるために
――XPRIZE Healthspanは賞金総額1億ドルということで、とても夢がありますよね。
吉森:賞金稼ぎだと思うとすごくアメリカ的ですが、分野を盛り上げるというのがこの財団の目的なんです。
おもしろいのは、敗退したチームや勝ち上がったチーム同士が合流するというのもアリなんです。競うことよりも、とにかく目標達成に近づけることを大事にしている。この「チームを組む」というのが非常によくて、たとえ優勝できなくても、その研究は今後に生かすことができますよね。
XPRIZEの前回のコンペテーマは月探査だったのですが、達成には至らず優勝者は出ませんでした。けれどもそれをきっかけにベンチャーが一部上場しましたし、投資家の目も集まって大きな力になったと思います。
また、こういうコンペに子どもたちの目が向けられて、研究者を目指すような子が増えればうれしいですね。
――今後、不老研究はどのように進んでいくでしょうか。
吉森:今日お話したことも人間で実証されているわけではないので、まだまだこの先の研究を進めて薬をつくるまでには長い時間とお金がかかります。
ただ、何十年も先ではないと思っているんです。というのも私の研究だけではなく世界中で研究は進んでいますので、思っているよりも早く実用化していくのではないかと期待しています。
賞金総額1億ドル!「10年若返る」を目指すコンペで、準決勝進出決定!
株式会社ファインは、株式会社AutoPhagyGO、キュレーションズ株式会社、株式会社電通のパートナー企業として、人間の健康寿命を10年(目標20年)延伸することを目指す世界規模のコンペティション『XPRIZE Healthspan』に参加している。
オートファジーを切り口とした細胞の老化制御に関する提案書「オートファジーリブーストプログラム」で、世界58カ国・600チーム以上の応募の中から、準決勝への進出が決定。さらに「Top 40 Milestone award」の受賞者にも選出された。
今後は臨床実験を2026年まで実施した後、さらに上位10チームとして決勝に選出されると、2029年まで2回目の臨床試験を経て2030年に最終審査が行われる。
吉森保先生
大阪大学名誉教授、同医学系研究科Beyond Cell Reborn学寄附講座教授
生命科学者、専門は細胞生物学。医学博士。1996年オートファジー研究のパイオニア・大隈良典氏(2016年ノーベル生理学・医学賞受賞)が 国立基礎生物学研究所にラボを立ち上げた時に助教授として参加。国立遺伝学研究所教授として 独立後、大阪大学微生物病研究所教授を経て、生命機能研究科と医学系研究科教授。2017 年大阪大学栄誉教授、2018~2022年生命機能研究科長。2024年定年により退職し、現職。 2013年文部科学大臣表彰科学技術賞、2019年紫綬褒章、他多数受賞。日本細胞生物学会会長(2016~2018年)。2019年大学発ベンチャーAutoPhagyGO Inc. を創業。一般社団法人・日本オートファジーコンソーシアム代表理事(2020~2024年) 論文の総被引用数が、分子生物学領域で国内2位、世界22位(2019年)。
