カッターナイフの“折る刃”は板チョコとガラスから生まれた!?【実は日本が世界初】

私たちが日常生活で当たり前のように使っている多くの技術や製品。それらの中には、実は日本で最初に開発され、世界中で普及したものが少なくありません。そんな意外と知られていない「日本が世界初」な技術や製品を紐解き、それが生まれた背景や世界に与えたインパクトなどをクローズアップします。今回は、折る刃式カッターナイフの歴史を紹介します。
折る刃式のカッターナイフ試作品が誕生

ビジネスパーソンであれば、オフィスの文房具に、折る刃式のカッターナイフが含まれていると思います。建築模型をつくったりプロダクトデザインを担当したりする人であれば日常的に使っているはず。倉庫、物流関係の仕事をしている人も携帯しているのではないでしょうか。
その折る刃式のカッターナイフ、実は日本で生まれたとご存じでしょうか。「カッターナイフ」という言葉そのものが和製英語で、小学館『大辞泉』にも、cutterとknifeを組み合わせた和製英語だと表記されています。
このカッターナイフは1956年(昭和31年)、後のオルファ株式会社(本社:大阪)の創業者である岡田良男さんと弟の三朗さんが印刷会社に勤務していた時代、紙を切る時に使っていたかみそりの代用品を求めて試行錯誤していった末に誕生したとされています。
カミソリの刃では安全面に問題があり、すぐに刃こぼれもしてしまうため、安全性が高い上に切れ味が長持ちする刃物が理想です。
その試行錯誤の過程で岡田さんは、いくつかの体験からヒントを得ます。第二次世界大戦後、進駐軍のアメリカ人兵士たちが、「ギブ・ミー・チョコレート」と口にする子どもたちに与えていた板チョコに溝が入っていて割れやすくなっていたことがひとつ。
さらに、戦後の靴の修理職人が、靴底を削る際に使っていたガラスの破片を、切れ味が悪くなるたびに折って使っていた姿がひとつ。
これらの体験から着想を得た岡田さんは1956年(昭和31年)、折る刃式のカッターナイフの試作品を世界で初めて誕生させるのですね。
特許を共有する形で取得
ただ、試作品づくりから商品化に至るまでに岡田さんは、多くの壁にぶつかりました。
以下は、各種の情報源に異なる記述が見られるので、正確性にやや欠けますが、岡田さんは1956年(昭和31年)、長さ約13cm、幅約1cm、折線のピッチ約5mmの試作品完成にこぎつけます。この年号については確定的な情報のようです。
販売にあたっては、資金提供者探しに難航したため、自己資金での販売に踏み切ります。ただ、大阪の鶴橋にある町工場が受注・製造してくれた3,000本の納品物が、サイズが異なっていたり、さやに刃が収まらなかったと、仕上がりがバラバラだったので、3カ月かけて自分で手直ししての販売となりました。
この販売時には〈シャープナイフ〉という商品名で販売したとの情報があります。
その後、資金提供者として、日本転写紙株式会社(現・エヌティー株式会社)の協力が得られると、岡田さん自身は同社に身を置きます。特許出願にあたっても、考案内容の発明者を岡田さんの名前にしつつ、出願人を日本転写紙にして、特許を共有する形で取得しました。
このあたりの年号は、情報源によって異なっています。日本転写紙(現・エヌティー)の公式ホームページによると1959年(昭和36年)、
“特許NTカッターを開発 “シャープナイフ”発売
世界初、シャープナイフ(現在名、カッターナイフ)の商品化に成功”(同社ホームページより引用)
とあります。この「発売」は恐らく、岡田さんが自己資金でつくった3,000本のシャープナイフとは異なり、日本転写紙と岡田さんの関係が始まった後、日本転写紙からあらためて発売された製品(シャープナイフ)についての記述だと考えられます。
- 試作(1956年)
- 岡田さん自身が3,000本を自力で発売(その間)
- 特許を共同取得し日本転写紙から発売(1959年)
という流れでしょうか。さらに、そのシャープナイフは、日本転写紙の頭文字から〈NTカッター〉と名称変更がされます。日本転写紙(現・エヌティー)の公式ホームページにはその時期が、1961年(昭和36年)とされています。
カッターナイフの刃の角度の秘密
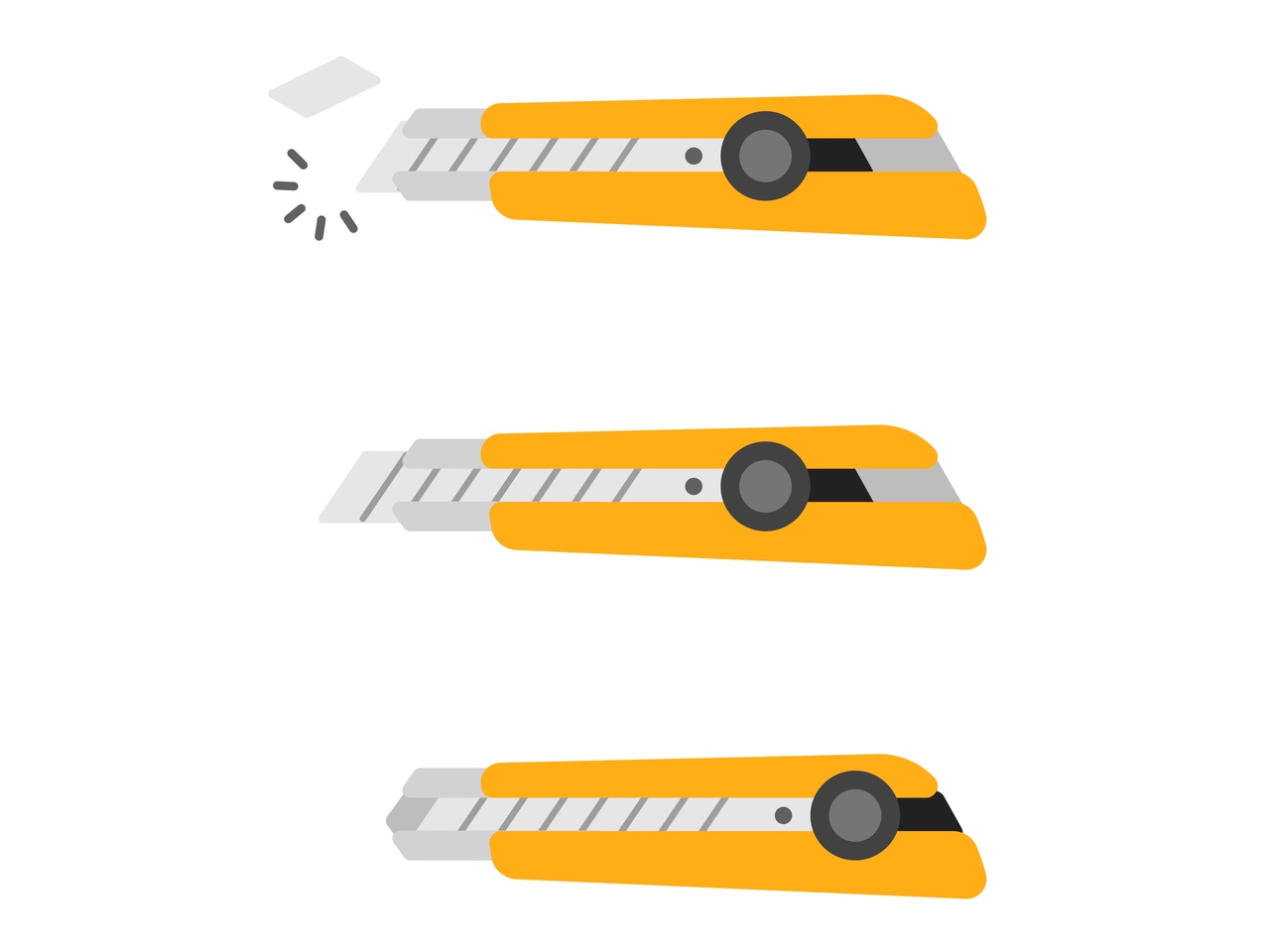
しかし、自分が生み出したカッターナイフを自分で売りたいという思いが強くなった岡田さんは1967年(昭和42年)、日本転写紙を退社し、岡田さんを含む男兄弟4人と岡田さんの配偶者とで岡田工業株式会社(現・オルファ株式会社)を設立します。
資金繰りが困難になり、極東ノート株式会社の資金協力を得て〈極東オルファカッター〉の名前で販売した時期もあったそうです。営業先でも、NTカッターの模倣品として扱われるなど、さまざまな苦労をしたそうですが、当時の有名な写真誌などに大きな広告を出し、1970年代のDIYブームとホームセンターの登場も追い風として受けつつ、徐々に軌道に乗せていったのだとか。
さらに、1970年(昭和45年)、北米の見本市でカッターナイフを見かけたカナダ人のウォルター・アブシルさんという人から、北米での販売について打診が届きます。そのカナダ進出を端緒に、同社の折る刃式カッターナイフは世界市場に受け入れられていくのですね。
以上が、日本で生まれた折る刃式カッターナイフの歴史となります。ちなみに、同社の社史を担当した大学の先生によると、オルファ社製カッターナイフの刃の角度は59度で、その角度は世界標準になっているのだとか。
どうして60度ではないのかと言えば、当時の分度器の精度が悪く、60度のつもりが59度になってしまい、今さら変える必要もないとの判断で温存されているみたいです。面白い話ですね。
[文/坂本正敬]
[参考]
※ 経営人類学者、「社史」を書く―「社史」作成からみえる「継ぐ」ということ― 帝塚山大学全学教育開発センター教授 岩井洋
※ 折る刃式カッターナイフ誕生秘話 – オルファ
※ 会社概要 – エヌティー
※ 折るナイフ – 服部国際特許事務所
※ 【SKIPの知財教室(IP Hack)】折る刃式カッターナイフの発明家 岡田良男(オルファ創業者) – SK弁理士法人
※ オルファについて – SEKAIDO