「簡体字」と「繁体字」どこが違う? 中国と台湾で“中国語”が別物に見える理由
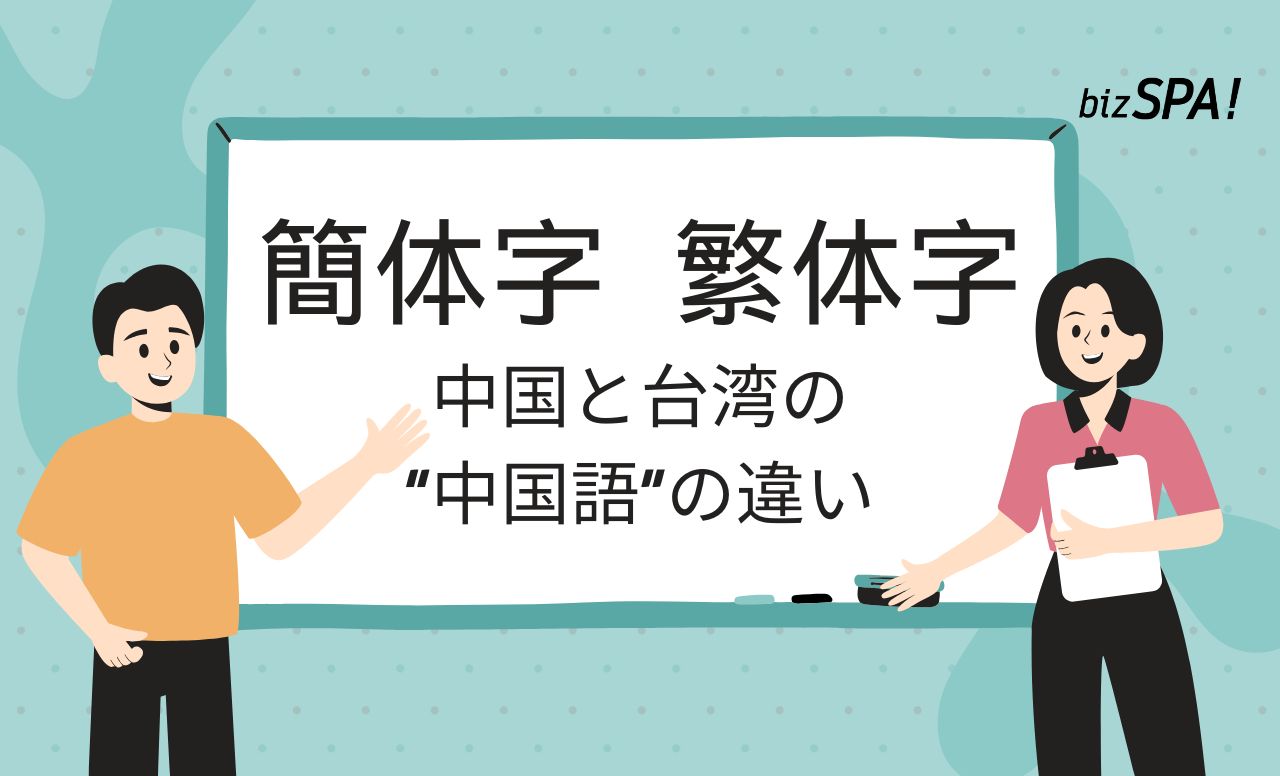
前回の記事では、中華圏(中国本土、香港、マカオ、台湾)の通貨事情についてお伝えしました。それぞれの地域で流通している通貨が違ったように、使われている言語についても独自の文化が現れています。この記事では、話し言葉に共通点の多い中国大陸と台湾で使われている言語について解説します。
関連記事:中華圏で使われる4つの通貨とは?中国・香港・マカオ・台湾のお金事情
【中国大陸】話者世界一の言語・普通話
公用語:普通話(標準中国語)
生活言語:普通話/地域では広東語、上海語などの方言多数
表記:簡体字
中国大陸では、法的に「普通話(プートンファー)」が公用語として定められています。行政や教育、公的な場面では普通話が使われます。地方ごとに広東語や上海語、閩南語などの方言も根強く、日常会話では普通話と切り替えて話す人も少なくありません。
中国では1950年代から漢字簡化が進められ、改定を重ねながら現在の簡体字体系が確立されました。これは識字率向上と教育の効率化を目的としたもので、以後、教育や出版物はすべて簡体字で統一されています。
発音表記には「拼音」と呼ばれるローマ字を用いた表記システムがあります。日本の学校で漢字の学習の前にひらがなの読み書きを行うように、中国語でも拼音の表記や発音から学び始めます。
また、辞書の発音注記のほか、PCやスマートフォンの入力方式など幅広く利用されています。
【台湾】普通話が通じるも文字は繁体字
公用語:國語(台湾華語)
生活言語:國語、台語(閩南語)、客家語など
表記:繁体字
台湾では、標準中国語(國語)が教育・行政の事実上の公用語となっています。生活言語でも國語が広く普及していますが、高齢者を中心に台語(閩南語)や客家語を話す人もいます。
教育・行政で使用される國語(台湾華語)は、中国大陸の普通話(プートンファー)と発音や文法の基礎は共通していますが、使用される表記は簡略化されていない伝統的な形を用いた繁体字となります。
簡体字と繁体字を比較すると以下のようになります。
(日本語:繁体字/簡体字)
電話:電話/电话
学校:學校/学校
体育:體育/体育
起きる:起床/起床
何を食べたい?:你想吃什麼?/你想吃什么?
簡体字と繁体字ですべての表記が変わるわけではありません。「起きる」を意味する「起床」は繁体字でも簡体字でも同じ漢字で表されます。「何を食べたい?」を意味するフレーズでは、疑問文で使う「么?」と「麼?」だけが違います。
また、語彙には台湾独自の特徴があります。
(日本語:普通話/台湾華語)
タクシー:出租车/計程車
弁当:盒饭/便當
さらに、普通話では読み方の補助としてローマ字を用いた拼音が使われますが、台湾では注音符号(通称:ボポモフォ)と呼ばれる独自の記号を使用します。

先日、台北を初めて訪れる機会がありました。地下鉄の優先座席の装飾に見慣れない文字が書かれており、後にこれが台湾華語の注音符号だとわかりました。
また、レストランや夜市、カフェでは、筆者の拙い普通話でも注文することができました。中国大陸とは違うところは、筆者が日本人だとわかると、すぐに日本語で金額や数を提示してきたことです。日本人が多く訪れるエリアでは、普通話よりも日本語で完結してしまうこともありました。
次回は、香港とマカオで使われている言語についてお伝えします。