廃止の方針が示された「作況指数」とは?【やさしいニュースワード解説】
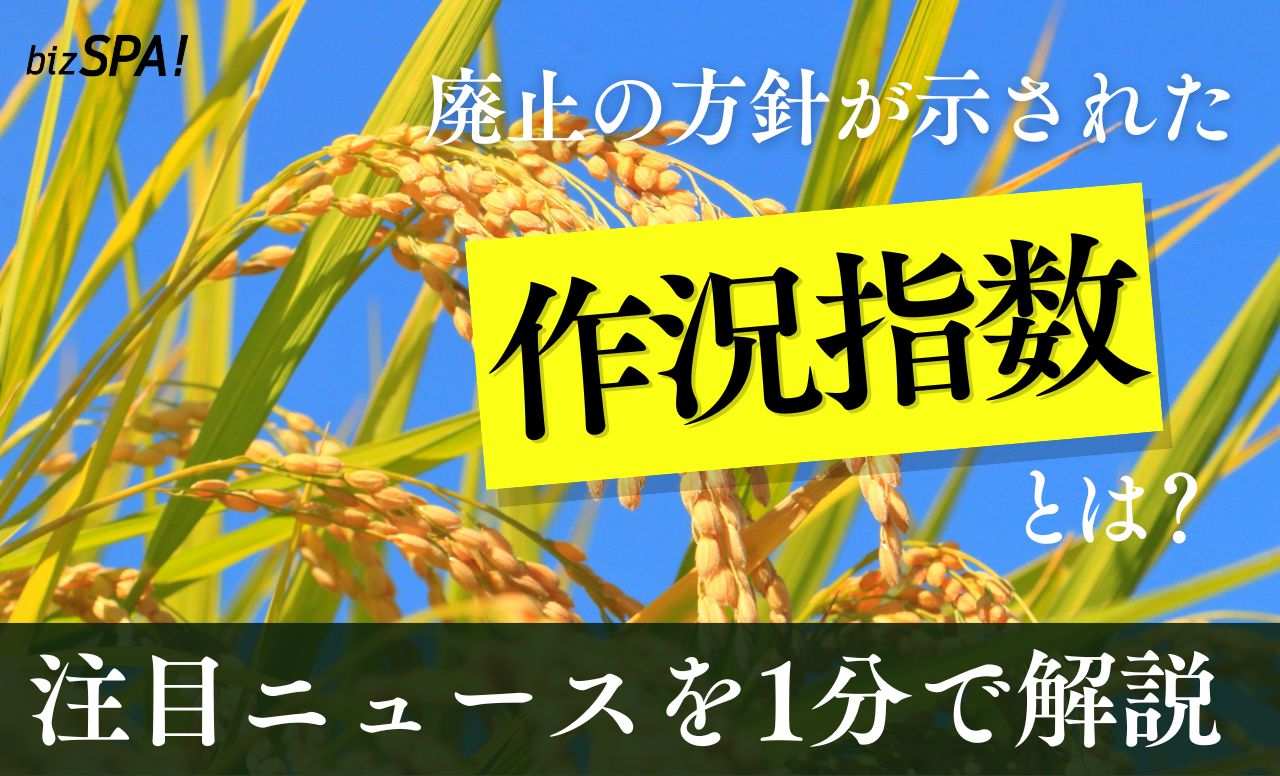
在京の大手メディアで取材記者歴30年、海外駐在経験もあるジャーナリストが時事ニュースをやさしく解説。今回は、「作況指数の廃止」です。
コメの作柄を示す「作況指数」が廃止に
小泉農水大臣はこのほど、コメの作柄を示す「作況指数」を2025年産米から廃止する方針を示しました。農水省の定義によると、作況指数はコメの作柄の良否を表す指標で、その年の「10アール当たり平年収量」に対する「10アール当たり(予想)収量」の比率で表します。
作況指数の公表は、10月中旬、11月中旬および12月上旬に行っています。小泉大臣は、農水省が発表する数字と生産現場の実感にずれがあることや、統計を扱う農水省の職員からの発案があったことなどを廃止の理由としています。
約70年にわたって続いてきた指標
農水省の基準によりますと、平年を100とした指数で、94以下が「不良」、95から 98が「やや不良」、99から101が「平年並み」、102から105が「やや良」、106以上が「良」となっています。 2024年(令和6年)産の全国の作況指数は101の「平年並み」でした。
ただ、約70年にわたって続いてきた統計だけに、指標として活用されている部分もあり、廃止に疑問の声があるのも事実です。作況指数に代わる指標や統計を今後どのように整備するのかという課題もあります。
1993年には「平成の米騒動」が
過去、作況指数が大きく注目されたのは1993年でした。天候不順による冷夏の影響で全国的にコメの生育が不良となり、収穫量が大きく減少しました。この年の作況指数は戦後最悪の74で、「著しい不良」でした。
コメ不足となった結果、タイなどからコメの緊急輸入が行われ、コンビニ弁当などでもタイ米が使われるなどの動きが広がりました。コメをめぐる話題が全国的に大きなニュースになったことから、「平成の米騒動」とも言われました。
食用米だけでなく日本酒への影響も
当時から30年以上の時を経たいま、「令和の米騒動」ともいわれるようにコメに関する話題が連日報道されています。コメ価格の上昇を受けて、価格対策としての備蓄米の競争入札による供給や、不適切発言による農水大臣の交代、その後の随意契約による備蓄米の供給、海外からの輸入などのニュースが続いています。
この結果、2024年(令和6年)産のコメや備蓄米など多くの種類のコメが流通することになり、価格帯も複数の層に分かれています。食用米の価格高騰を受けて、酒造りに使う酒米の価格も上昇し、日本酒の生産者が窮地に陥るなど、影響は拡大しています。
今後、梅雨明けから真夏にかけて天候の推移や稲の成長具合が気になりますが、収穫の秋にコメの生産量が最終的にどうなるかが注目されます。収穫量次第でコメの値段が大きく左右されることになり、今年はコメから目が離せない年となりそうです。