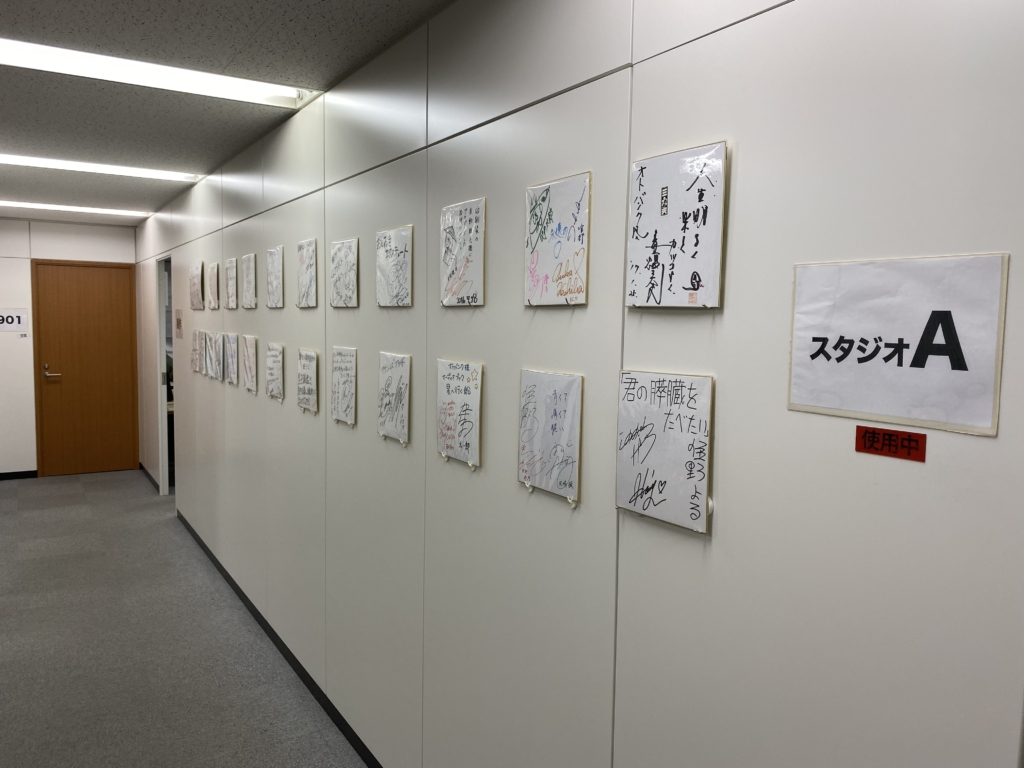通勤中に“本を聴く”人が急増中。朗読アプリ運営会社の狙い
環境さえ整えば日本でも勝算があった
――ユーザー層はどういう人たちですか?
久保田:5~6年前ぐらいまでは30代男性が多かったんですが、近年はだいぶバラけてきていて20~70代と、かなり多様になってきました。
――売れ筋はどういうもの?
久保田:ビジネス書や自己啓発系の本、それからコミュニケーション術といったものはコンスタントに人気があります。あとは、分厚い本もよく売れています。ベストセラーになった『サピエンス全史』などがそうですが、分厚い本もオーディオブックなら消化できるのかもしれません。
――「アメリカは車社会だから朗読コンテンツが普及したけれど、日本はそうじゃないから普及しない」という説があるようですが、どうなんですかね?
久保田:実際に各国のデータを調べてみたら、日本と同程度の国土であるイギリスやドイツでも、朗読コンテンツは非常に普及していたんです。日本は何が違うのかと考えると、コンテンツの量が圧倒的に違いました。それから、ドイツでは薬局で朗読CDが売られていたりして、身近なところで手に入る仕組みも整っていたんです。十分なコンテンツがそろうようになれば、日本でもオーディオブックコンテンツは広がっていくはずだと考えています。
記者にニュースの解説をしてもらいたい
――今後やりたいことは?
久保田:オーディオブックはもちろんですが、本を音声化する以外のコンテンツも増やしています。たとえば、最近では媒体と連携し、記者として週刊誌やネットニュースの編集部の人に登場してもらって、15分間ぐらいの短めの尺で記事の解説をしてもらう音声コンテンツの配信を開始しました。
音のコンテンツを聞いているときって、脳みその可動領域が余るので、映像に比べてモノを考えやすいんです。批判するとしても、一方的に怒るというより、理路整然と意見を言う人が多い。記事の解説を音声で聴けるようにすることで、読み手の理解もさらに促進して誤解による炎上なども防げたらと思っています。
<取材・文/西谷格>