公務員はTikTokやめた方がいい!? 利用禁止法を諸外国が次々と成立させる理由
国家情報法のある中国においては、国家の情報活動にあらゆる組織や個人が協力しなければいけない。
・関連記事
>>>中国旅行・出張中のチャット内容で拘束も。人ごとじゃない「スパイ容疑」回避の心得
動画共有アプリ〈TikTok〉を運営するByteDance社(北京)も当然、中国政府に求められれば、利用者の個人情報を提供する可能性は否定できない。そのリスクが、各国の安全保障に影響を与えると言われている。
例えば、特定の国で力を持つ政治家または官僚の個人情報が〈TikTok〉の利用履歴を通じて中国政府に把握され、国家の安全保障を脅かすような交渉材料にされる恐れがあるという。
その懸念を深刻にとらえ〈TikTok〉の利用を一部禁止する法律が海外で成立し始めている。若者を中心に利用者が広がる〈TikTok〉をなぜ諸外国が禁じようとするのか。
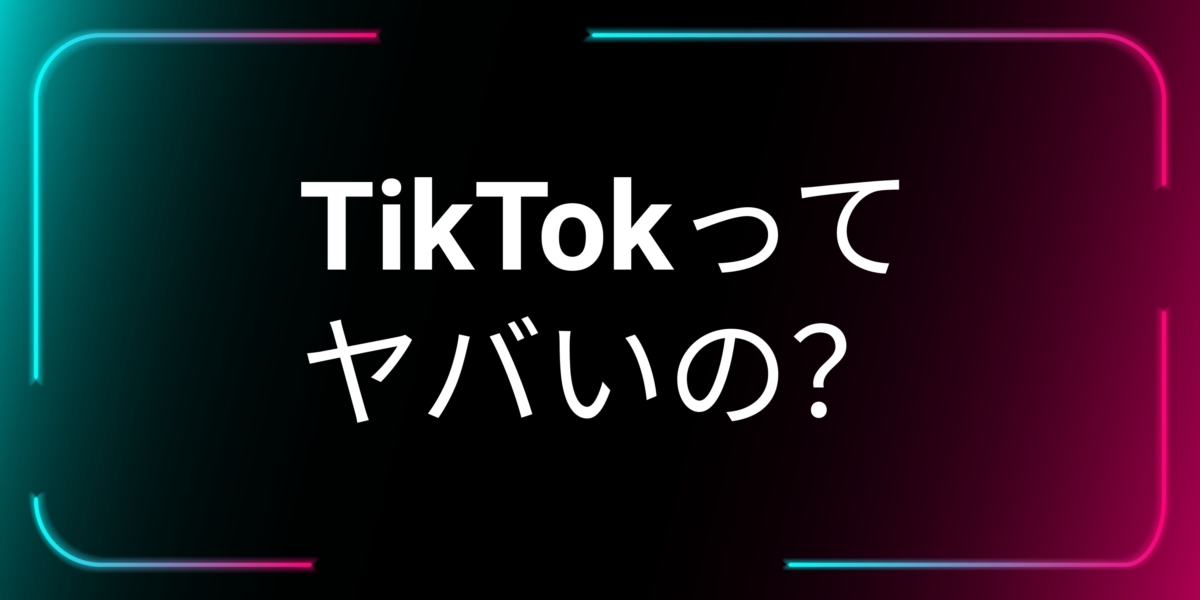
そこで今回は、国際安全保障や経済安全保障などを専門とする和田大樹さんに、その背景を教えてもらった(以下、和田大樹さんの寄稿)。
安全保障上の懸念がTikTokにある
アメリカのバイデン大統領は4月末、中国企業ByteDance社が運営する動画共有アプリ〈TikTok〉の国内利用を禁止する法案に署名した。
米国議会下院が3月中旬、安全保障上の懸念があるとして同法案を可決してから、極めてスピーディーな今回の動きとなった。
今後9カ月から1年以内にByteDance社が米国での事業を売却しなければ、米国での利用が来年にもできなくなる。
米国だけではない。近年では、カナダや英国、ベルギーにおいて、各国の政府機関などの公用端末で〈TikTok〉の利用を禁止する法案が可決された。
対岸の日本から見ていると、ちょっと過剰な反応にも見えるが、その背景には何があるのか。
安全保障の前では自由や人権、経済は制限される
bizSPA!フレッシュ読者には周知のとおり〈TikTok〉は若者を中心に人気がある動画共有アプリだ。
その利用を禁止する動きに対しては当然、表現の自由を制限するとの反発も広がっている。
〈TikTok〉運営側も“1億7000万人のアメリカ人の言論の自由を踏みにじり、700万社のビジネスに壊滅的打撃を与え、アメリカ経済に年間240億ドル(約3兆117億円)貢献しているプラットフォームを閉鎖することになる”(英BBCのウェブ版より引用)と強く反発している。
現時点で、日本国内では〈TikTok〉が自由に使えるが、安全保障を優先するか、自由・人権・経済を優先するかの問題である。考え方や価値観が人によって異なる。万人が納得する答えは出ない。
その中で今後、国際政治の動きから言えば、こういった規制は強化されていくだろう。安全保障が絡む問題では、自由や人権、経済といった領域に制限が設けられるのだ。
相手国が漏えい洩を懸念する情報をいかに掴むか
米中対立を例に挙げる。今日、米中は、台湾情勢や中国軍による海洋進出の安全保障分野に加え、経済や貿易、人権、先端技術といった多岐に渡る分野で競争と対立を展開している。
・関連記事
>>>半導体競争で中国が勝つと国防の危機も。世界の半導体レースが行き着く先は?
双方の間では、相手の重要な情報をいかに掴むか、取られたくない情報をいかに守るかが至上命題になっている。今日の世界は情報戦とも言われている。相手国が漏えいを懸念する情報をいかに掴むかが重要になっている。
秋の米国大統領選挙では、現職のバイデン大統領とトランプ氏の再戦となるが、中国に対して双方とも厳しい姿勢で臨む方針だ。中国企業や中国製品への警戒感をどちらも強く持っている。
・関連記事
>>>バイデンとトランプの意外な共通点。2人の奇妙な連続性と「世界の警察官」を卒業する日
米国の中国に対する厳しい姿勢はどちらが勝利しても来年以降の4年間続く。激しい米中対立は避けられない。
もちろん、政治的なパフォーマンスの側面も一部に指摘されているが、国際政治の視点から言えば、今回のような対中規制(いわゆる「TikTok禁止法」)は米国で一層強化されるだろう。
日本ではすぐに規制が掛かりはしないだろう。ただ、日米同盟を基軸にする日本にも追従の動きが起きる可能性はゼロではない。
[文・和田大樹]
[参考]
※ なぜダメなの?TikTok 世界に広がる禁止包囲網 – NHK
※ TikTok、全米での配信禁止は「言論の自由を踏みにじる」 米下院での法案可決に反発 – BBC