ニッチとは?意味や建築での使い方を解説【いまさら聞けないビジネス用語】
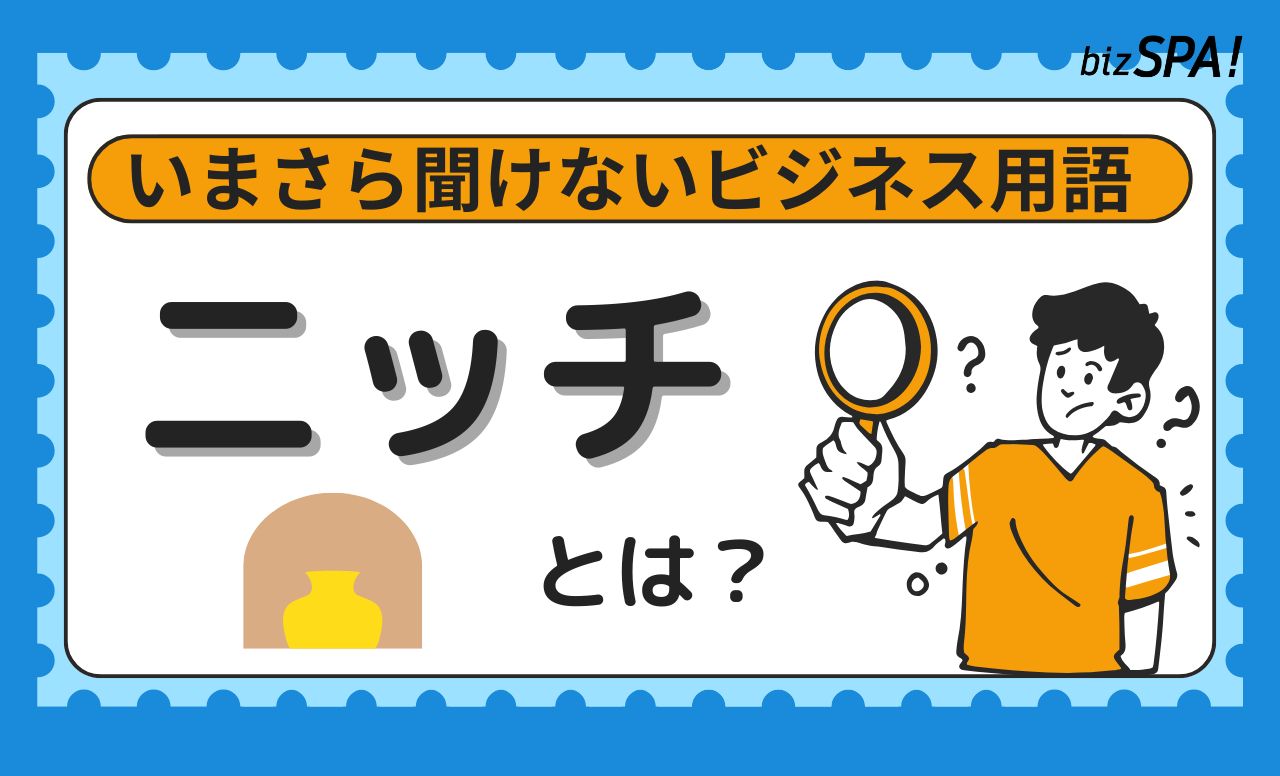
ビジネスシーンにおいて、適切な言葉遣いは重要なスキルのひとつ。基本的なビジネス用語を理解していることは、コミュニケーションの円滑化に直結します。本記事では、いまさら人に聞けないけれど、知っておきたいビジネス用語をわかりやすく解説。それぞれの用語が持つ背景や使用されるシチュエーションを押さえておくことで、職場での会話やメールに自信を持てるようになります。今回は「ニッチ」について、その意味や建築での使い方、ニッチビジネスのメリット・デメリットを紹介します。
目次
「ニッチ」とは隙間、特定の市場や分野という意味
ニッチは、ラテン語の「nidus(巣)」に由来するフランス語の「niche(小さなくぼみ、奥まったところ)」を語源とし、英語では「特定の市場や分野」「隙間」「適所」などの意味がある言葉です。日本でビジネス用語として使われる場合は、特定の分野や市場における小規模ながらも独自性のある領域などの意味合いが強くなります。
ビジネスにおける「ニッチ」とは
ビジネス分野では、「ニッチ市場」や「ニッチビジネス」といった形で使われます。これは、競争が激しい大規模な市場ではなく、特定のニーズを持つ小規模な市場を対象に成功を目指し戦略を展開することです。
ニッチ市場とは、大手企業が参入しにくく、あるいは参入していない特定のニーズが存在する市場のことです。大衆向けの市場に比べて、ターゲットとなる顧客層が限られていること、一般的な製品やサービスでは満たせない、独自のニーズを満たすことを目的としていることなどが特徴です。
大手企業が参入しにくいことから、新規参入が比較的容易な場合があったり、特定の価値を提供することで、ブランドへの高い関心を持つ顧客を得られる可能性があったりします。そして、このような市場を狙いさまざまなサービスや商品を提供するのが「ニッチビジネス」です。
各業界のニッチ市場の具体例は下記のようになっています。
ファッション業界
・超小柄・超高身長専用の服など特定の体型に向けたブランド
・1点物のオーダーメイドのカバンや靴の専門店 など
食品業界
・ヴィーガン(完全菜食)やグルテンフリー専用の食品メーカー
・特定のアレルギー対応食品専門のブランド など
旅行・サービス業界
・ペットと泊まれるラグジュアリーホテル
・ダイビングや野鳥観察といった特定の活動に興味を持つ方のための旅行 など
ニッチビジネスのメリット・デメリット
ニッチビジネスには多くのメリットがありますが、反対にデメリットも少なくありません。ここでは、ニッチビジネスのメリットやデメリットについて詳しくご紹介します。
メリット
まず大きなメリットとして、大手企業が参入しない市場を目指すため、価格競争が起こりにくいことが挙げられます。独自性が強いため価格を高く設定でき、賛同する方が増えれば大きな利益につながることもあるでしょう。
また、特定のニーズに特化しているため、ブランドの差別化がしやすく、その業界では多くの認知を得られる可能性もあります。熱心な顧客を獲得することができれば、その後新たな参入者がいても顧客が離れにくいのもメリットです。
デメリット
ニッチビジネスのデメリットとして、市場規模が小さく目標が限定的なため、大きな売上を確保しにくいことが挙げられます。一定の売上を上回ると拡大が難しくなり、将来的に衰退してしまう可能性もあるでしょう。
さらに、市場変化の影響を受けやすいこともデメリットとして挙げられます。技術革新や社会の変化などによって、ニーズがなくなるリスクは否めません。
建築業界における「ニッチ」とは
ニッチという言葉は、建築の分野でも使われる言葉です。建築分野でのニッチは「壁の一部をくぼませた空間」のことを指し、小物や絵、花瓶などを置くスペースとして使われたり、スイッチやインターフォン、給湯器のコントローラーなどをまとめて設置するスペースとして使われたりすることが多いです。
また、それ以外にもキッチンの調味料置き場として、バスルームのシャンプー置き場としてなど、住宅のさまざまな場所で活用できるスペースでもあります。上手に取り入れることで、利便性向上や装飾性の向上などを実現できるでしょう。
新たなビジネスチャンスの場所でもあるニッチ市場
前述のように、ビジネスにおける「ニッチ」とは、大手企業が参入しにくい特定の市場やニーズに焦点を当てたビジネス戦略のことです。大手企業が参入する業界では成功が難しいケースや、独自の製品やサービスで勝負したいという方は、ニッチ市場を狙うことで大きな成功を収められる可能性があるでしょう。
ただしニッチビジネスを成功させるには、ターゲット市場のリサーチを徹底し、専門性を活かした商品・サービスの提供や適切なマーケティング戦略が必要です。必ずしも大きな成功につながるとは限らないため、リスクも踏まえたうえで進出を検討するといいでしょう。
