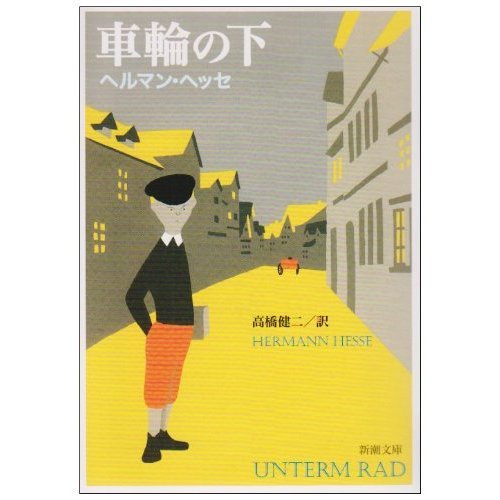受験エリートの転落人生…ドイツ文学の金字塔が描く、人生の深い意味
主人公は才能に恵まれた神童
なお、一歩離れてこの小説を読むと、この父親はそこまで悪い父親でもない。息子を心配して手紙を書くし、後に仕事も探してくれる。俗物なりにいい父親に思える。
そんな家に生まれたハンスは才能に恵まれた神童である。ラテン語、ギリシャ語、数学を難なくこなす。通っている学校の校長も期待をかけるし、担任はじめ教師はハンスのために受験の特訓をおこなう。
すべては神学校への切符である「州試験」合格のためである。なんせこの州試験、ハンスの村から受けるものはハンス一人しかいない。
ついに試験当日。各地から集まったライバルに「この問題は簡単だった」と言ってみたり、相手に知らない文法用語を話されて不安になったり、このあたりはまさに受験あるあるだ。
十で神童、十五で才子、二十歳過ぎれば…
中高大どこかで受験を経た人ならばむずがゆい思いになるだろう。不安にさいなまれるハンスだが、結局は2位という好成績で合格する。
物語はここからである。「十で神童、十五で才子、二十歳過ぎれば只の人」ということわざをきいたことがあるだろう。まさにそうした状況だ。ここから主人公ハンスはどんどんと道を外れていく。
ハンスはめでたく全寮制の神学校に入れた。現在の日本でいえば中高一貫の名門進学校入学といったところだ。寮の同室9人のうち4人は個性豊か、残りは普通の優等生。同室の生徒には大学教授の息子、度を越した節約家などがいてハンスは圧倒される。その中のひとり、詩とバイオリンをたしなむハイルナーにハンスは惹かれていく。
ハイルナーは問題児だが自分をしっかりと持っているタイプだ。勝手に遠出して、知らない村の警官と仲良くなり、さらに村人を紹介してもらって一宿一飯をおごってもらうという具合にエネルギーにあふれたエピソードに事欠かない。