“残業キャンセル界隈”“静かな退職”が話題!Z世代社員の離職の実態と解決策とは?
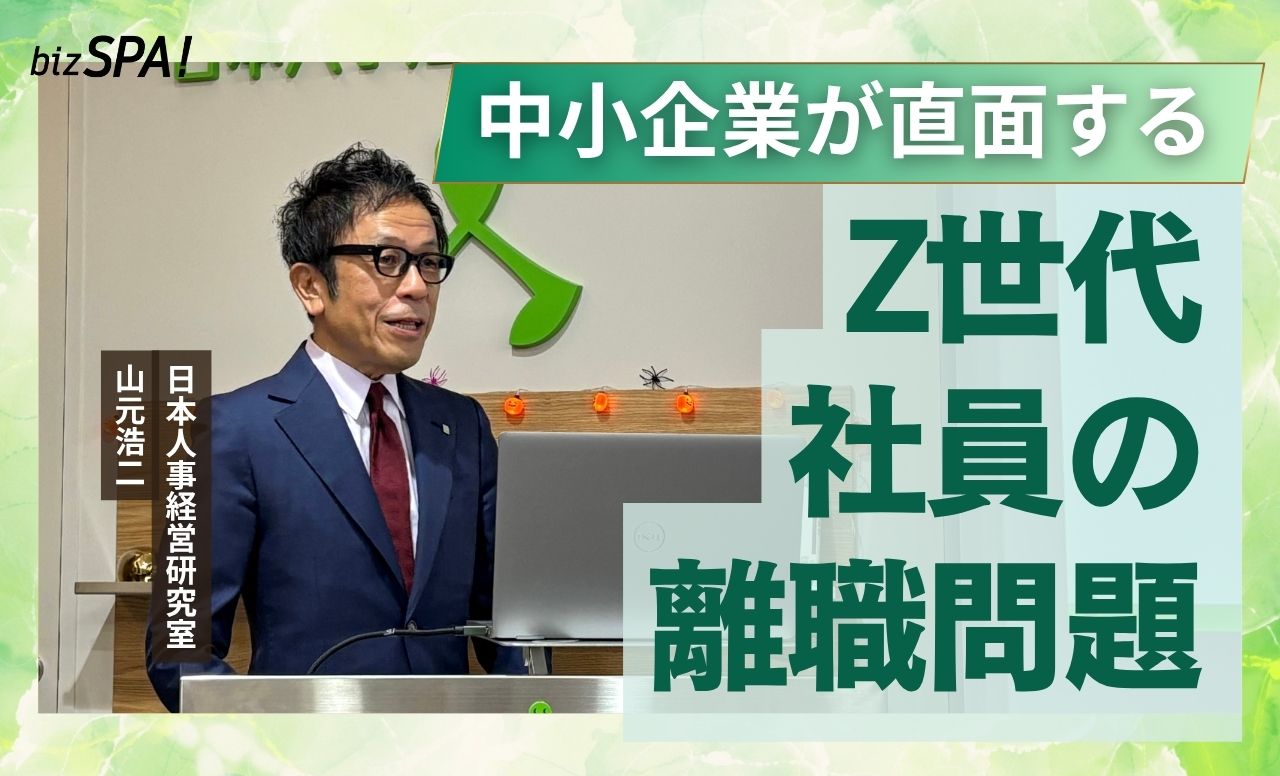
多くの業種で人手不足が深刻化する中、最近では、仕事が残っていても定時に帰る「残業キャンセル界隈」や、退職はせずとも最低限の業務のみをこなす「静かな退職」といった言葉が話題となるなど、経営者と働き手の考え方のギャップが浮き彫りとなっています。
中小企業の人事評価制度の構築・運用をサポートする日本人事経営研究室株式会社は2025年10月9日(木)、中小企業が直面している「Z世代社員の離職問題」をテーマにラウンドテーブルを実施。同社の山元浩二代表取締役が、現状の課題と解決策について解説しました。そのポイントを紹介します。
目次
若手の退職増、社員のモチベーション低下が課題
山元代表は、「今の中小企業は、若手、特にZ世代の退職が増え、社員のモチベーションも低下しているという大きな課題を抱えている」と警鐘を鳴らします。さらに、山元氏は「中小企業の1人当たりの稼ぎや生産性は、大企業の約3分の1しかない」という日本の経済課題の根幹にも触れ、このままでは日本の発展自体がないと危機感を示します。
しかし、この課題の解決策は、単なる若手への「配慮」や「特別扱い」ではありません。中小企業が抱える課題の解決は、若手ビジネスパーソンのキャリアと成長に直結する、重要な「仕組み」の変革だといいます。
転職の常識が覆った「外部環境」の変化
まず、若手社員の離職が増える背景には、企業側ではどうにもできない「外部環境」の大きな変化があると山元代表は指摘します。
一昔前は、転職すれば給料は下がるのが一般的だった一方で、今の日本は転職すればほとんどの年齢層で給料が上がるという状況にあり、転職へのハードルが劇的に下がっています。実際に、新社会人の転職サイト登録者数は、約14年間で31倍にも増加しており、いつでも転職できる環境が整っているのです。
かつては「終身雇用」を前提に、会社に尽くすことが美徳とされましたが、今は「辞めたくなったら転職して、給料を上げる」という選択肢が現実的になっています。
企業と社員のギャップの正体は「成長機会への飢餓感」
外部環境の変化に加え、組織の中で入る前と後で若手社員が感じるギャップという「内部の問題」が離職を加速させていると、山元代表は分析します。
日本人事経営研究室の独自調査では、Z世代社員の約3割が、入社半年で既に退職を検討したことがあるというのです。
また、転職理由のトップは「給与や待遇への不満」ですが、その裏には「評価制度」の問題が潜んでいます。さらに、「仕事のやりがいがなかった」「自分自身の将来性に不安を感じた」も上位に挙げられており、待遇面の不満だけでなく、自己成長への意欲が満たされていないことが大きな要因となっているのです。
この「成長意欲」と「現実」のギャップは深刻です。「成長機会が足りない」と感じているZ世代社員の割合は、経営側が「十分に機会を与えている」と感じている割合の約6倍にも上るという調査結果もあります。
山元代表は「評価が本人に伝えられて、その評価結果に対する賞与・昇給に納得できる仕組みが確立できていれば、給料への不満は圧倒的に減るはずだ」と断言。つまり、若手社員が求めているのは、「頑張りが正当に評価され、自分の将来につながる」という納得感と透明性なのです。
経営計画と人事評価制度を連動させる「ビジョン実現型人事評価制度」
山元代表が中小企業に提唱し、766社(2025年10月時点)で導入を支援しているのが「ビジョン実現型人事評価制度」です。これは、「経営計画」と「人事評価制度(評価制度・賃金制度・昇格制度)」の2つを連動させて運用するという仕組みで、これにより以下のような変革が生まれるといいます。
・ベクトルの一致と生産性向上
経営計画で組織全体のビジョンが明確になり、社員全員が会社の目指すゴールを理解し、バラバラだった仕事の方向性がそろう。結果として、組織全体の推進力は「3倍、5倍、10倍」と成長を実現できる。
・キャリアの可視化とモチベーション向上
組織のビジョンと連動した自分自身の成長計画が、評価制度を通じて明確になる。これにより、社員一人ひとりが中長期的な将来の年収目標や、いつどのくらいの役職になれるかというキャリアパスを具体的に持つことが可能に。
山元代表は、「社員一人ひとりが将来の年収目標を明確にできると、会社での人生設計も具体的に持てるようになる」と、その効果を強調します。
対話を重視した仕組み導入による成長の成功事例
「ビジョン実現型人事評価制度」を導入し、若手社員の定着に成功している企業からの事例発表もありました。
早稲田大学発ベンチャーとして神社仏閣のコンサルティングを行う株式会社Elternalの小久保隆泰社長は、業績を順調に伸ばしていたものの、初期は「生きるか死ぬか」の勝負だったため、経営計画や人事評価制度は未整備だったといいます 。
社員が20〜25人に増えていく中で、スタッフのベクトルを合わせることに苦慮していた小久保社長は2024年7月に制度を導入。すると、社員のベクトルがそろい、生産性の向上や若手のスピード昇格(出世)といった変化があったそうです。
「キャリアパスが明確になってモチベーションが上がり、これをすれば上に行けるということが明確化されたことによって昇進者が誕生しました」と小久保社長は語ります。特に、新卒入社から1年半〜2年目でスピード出世した25歳の社員や、一般社員からすぐに執行役員に昇格した30歳の社員の例を挙げ、「やる気のある社員がしっかりと評価され、よりモチベーションが高まる」とその効果を強調します。
また、熊本県で建設業・飲食業を展開する鈴木電設株式会社の鈴木健太社長は、「人事評価制度というのは、評価をすることではなくて成長支援の場だ」と捉えています。
同社では、この「成長支援」を実現するために、求めることをはっきり伝える明確なコミュニケーションや頑張っているところを意識的に褒める毎月の面談、役職に応じたグレード別勉強会を行っているそうです。
その結果、社員同士が高め合い、離職が減り、社長自身は新規事業の開発に注力できる環境を実現しました。実際に、導入前の建設業中心の事業から、この4年で4つの事業体を持つまでに成長しています。
中小企業の変革がビジネスパーソンの未来と日本経済を拓く
山元代表は、日本の99.7%は中小企業であり、労働人口の7割がそこで働いている現実を指摘し、「ここが変わらないことには日本の経済も日本の発展自体もない」と強調します。そして、この変革を牽引するのは、他でもない「中小企業の社長」です。
・ビジョンを低く設定する「諦め」からの脱却
・社長が「一人プレイヤー」であるマネジメントの属人化からの脱却
これらの課題を克服し、経営計画と人事評価制度を連動させることで、中小企業は「成長できるんだ」ということを示すのが、山元代表のミッションです。
若手ビジネスパーソンにとっても、これは単なる人事制度の話ではありません。「成長の機会がない」と不満を持つのではなく、会社の仕組みを理解し、能動的に活用することで、自己成長を加速させ、結果として会社と日本経済の未来を牽引する存在となれるはずでしょう。