ノートPCは日本生まれ!1989年発売の「DynaBook」は19万8,000円だった【実は日本が世界初】
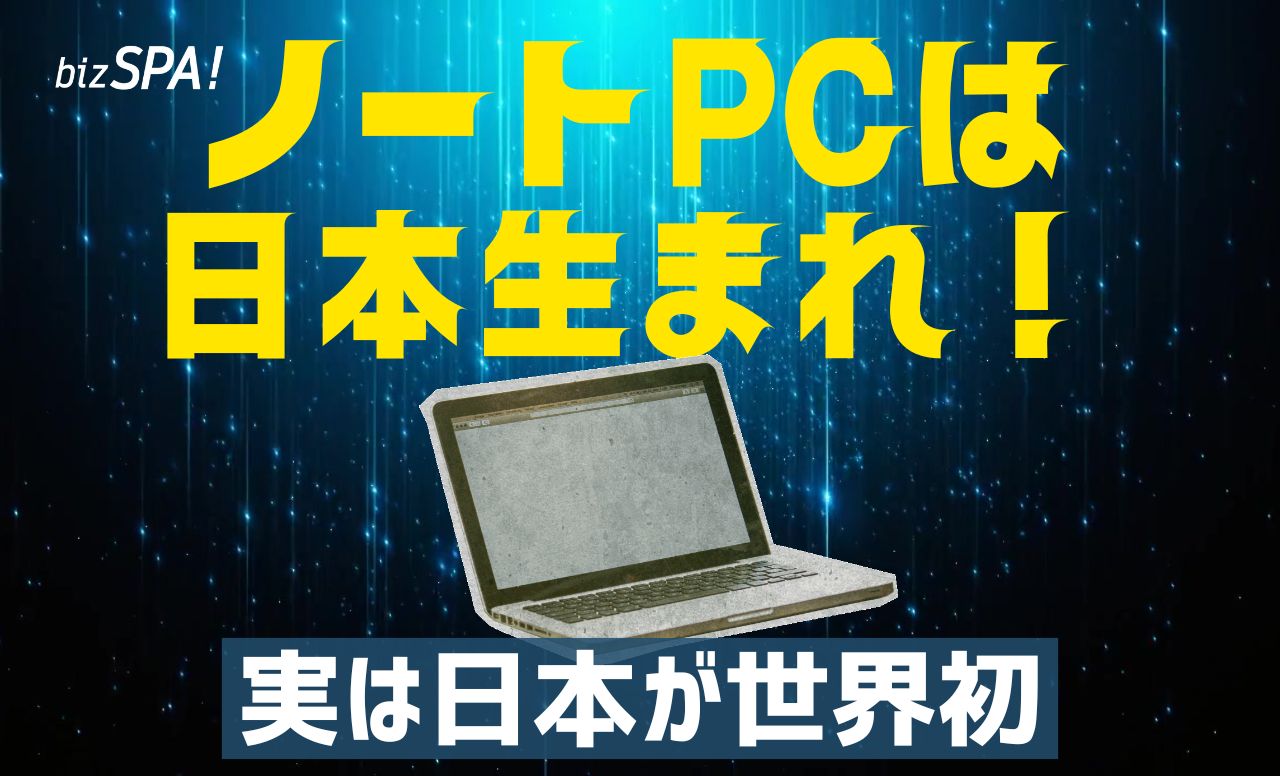
私たちが日常生活で当たり前のように使っている多くの技術や製品。それらの中には、実は日本で最初に開発され、世界中で普及したものが少なくありません。そんな意外と知られていない「日本が世界初」な技術や製品を紐解き、それが生まれた背景や世界に与えたインパクトなどをクローズアップします。今回は、社会人の多くが業務の中で使うノート型パソコンを紹介します。
世界初とされるノート型PC「Dynabook」
ノート型パソコンの歴史を語る前に「ノート型パソコン」とは何か、各社の百科事典でその定義をおさらいしておきましょう。
- ・大きさがおよそB5~A4版
- ・重量が1キロ~3キロ程度
- ・外出先での使用を前提
- ・バッテリーを本体に搭載
- ・ディスプレイとキーボードを一体化
以上のような小型パソコンを「ノート型パソコン」と一般的に意味するみたいです。
では、この小型の持ち運び可能なパソコンを最初につくった会社はどこなのでしょうか?
答えは、一般的な見解として東芝だとされています。東芝のノート型パソコンブランドに〈Dynabook(ダイナブック)〉があります。1989年(昭和64年・平成元年)、
“世界初のノートPC”(東芝の公式ホームページより引用)
として東芝がリリースしたあのブランドシリーズの初号機が、外に持ち出せるノート型パソコンとして世界で初めてリリースされたと一般に認知されています。
この「DynaBook J-3100 SS001」は、A4サイズ、重さ2.7キロ、価格19万8,000円。パーソナルコンピューターの概念を覆す製品として全世界に衝撃を与え、当時の世界シェア最大手へ東芝を押し上げるきっかけにもなりました。
ノート型パソコンの始祖「T1100」
しかも、このDynabookの誕生以前の1985年(昭和60年)に〈T1100〉というポータブルパソコンも東芝は販売しています。このパソコンは、ドイツで最初に発表され、約1万台を売り上げました。
後の2013年(平成25年)に、世界最大の電気・電子関係の学会であるIEEEから「IEEEマイルストーン」に選ばれている点を見てもT1100こそ、現代のテクノロジーに大きなインパクトを与えたノート型パソコンの始祖と言ってもいいのかもしれません。
1台のデスクトップ型パソコンを複数の人がシェアし、パソコンの設置されている場所に人が動いて使用した時代に、バッテリー駆動で動かし、外に持ち出せるようにした最初のパソコンです。当時のパンフレットには、
“So small, it’ll virtually fit in a briefcase”(東芝のパンフレットより引用)
と書かれています(「とっても小さくて、物理的に、ブリーフケースに入る」の意)。
ノート型パソコンの定義には、大きさがおよそB5~A4版、重量が1キロ~3キロ程度という条件がありました。
T1100の大きさはB4版(約257mm × 364mm)程度、重量は4.1キロと、現代のノート型パソコンの定義には少し合わないかもしれませんが、ぎりぎり持ち運べるサイズではあります。
さらに、クラムシェル(二枚貝の殻)の形を採用し、8時間のバッテリー駆動を実現していた点は、ノート型パソコンの始祖と言われるゆえんです。
誰もが気軽に持ち運べるコンピューターの誕生
ただ、T1100には、弱点がありました。ハードディスクが搭載されていません。フロッピーディスクでデータを記録するため用途に限界があります。
そこで東芝は、ハードディスク内臓のポータブルパソコン〈T3100〉を翌年の1986年(昭和61年)にリリースし「いつでも、どこでも、だれでも」というコンセプトの実現にさらに近付きました。
この先行モデルを土台に、
“3年後には、ビジネスマンがカバンに入れて持ち運べるPCを作る。すなわち、A4サイズ、質量3kg、パーソナルユースのために手ごろな価格”(〈東芝レビュー〉より引用)
を目指すという方向性が示され、1989年(昭和64年・平成元年)に世界で初めて、コンピューターを誰もが気軽に持ち運べる製品(Dynabook)の誕生につながっていくのですね。
ちなみに「Dynabook」とは「パーソナルコンピュータの父」とされるアメリカ人のアラン・ケイが1960年代後半に提唱した言葉です。
「子どもでも使える、直感的に使える、持ち運び可能なコンピューター」を意味する言葉で、東芝の製品名とは直接的に関係がないものの(東芝の製品は、アラン・ケイの考える理想のコンピューターとは別物であると本人が評価)、世界各国のコンピューター開発者に大きな影響を与えました。
実際に今、アラン・ケイの提唱した「Dynabook」は実現したのでしょうか。実現したとすれば、どの会社のどの製品から実現されたのでしょうか。その辺も併せて考えてみると、身近なノート型パソコンに対する見方が深まるかもしれませんね。
[文/坂本正敬]
[参考]
※ Toshiba T1100 — why a laptop without a hard drive was named an IEEE milestone of electronic engineering? – Medium
※ T1100 – コンピューター博物館
※ ラップトップPC「T1100」が「IEEEマイルストーン」に認定 – TOSHIBA
※ ラップトップ PC T1100 – でんきの礎
※ dynabookの歩み – TOSHIBA
※ ノートパソコン – 東芝レビュー
※ 東芝、ダイナブックの父からの宿題 危機の時こそ破壊を – 日本経済新聞
※ 人類の進化を加速させた「手で触る情報操作」子どもの創造的学習意欲を刺激するパソコンは、ここから始まった – NEC